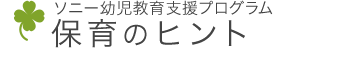![]()
ソニー幼児教育支援プログラム 幼児教育保育実践サイト
保育のヒント ~科学する心を育む~
- トップ >
- 20210909 メダカ~卵との出合い~
保育のヒント~「科学する心」を育てる~
メダカ~卵との出合い~/草津市立矢倉幼稚園(滋賀県)
 子どもたちと、小さな生き物との関わりに焦点を当てて継続して記録を取ることはありますか?
子どもたちと、小さな生き物との関わりに焦点を当てて継続して記録を取ることはありますか?
今回は、メダカの飼育の過程で、子どもたちのつぶやきを見逃さずに丁寧に記録を積み重ねている園の事例をご紹介いたします。メダカの卵との出合いの喜び、小さな赤ちゃんメダカにも目があることへの気づきと感動など、子どもたちは「科学する心」につながる豊かな体験をしています。保育者は、事例を丁寧に振り返り、一人一人に注目して、変容や育ちを読み取っています。
メダカとの関わり/4歳児
場面1(6月)「メダカさん、お腹に卵付いてる!」~初めてのことに出合う~

- 「なんかついてる」

- カップに入ったメダカを見る子どもたち
前年度から引き継いだメダカに加えて職員が新たにメダカを3匹持ってきた。子どもたちは喜び、その日から「自分たちで世話をしたい」と、メダカの飼育が始まった。
ある日、Aさんが、いつものようにメダカに餌をあげていた。そして、メダカが水面に浮かぶ餌を食べている様子を見ながら「あれ?お腹になんか付いてる」と気づき、「先生、見て!」と伝えてきた。保育者は何であるか分かっていたが、「何やろ。誰か分かるお友達いるかなぁ」と受け止めて話した。
するとAさんはBさんを呼びに行く。Bさんは、祖父母がメダカを飼育していて、メダカのことをよく知っている。Bさんは見てすぐに「あ、卵や!」と話し、「メダカさんのお腹に卵付いてるでー!」と他の友達にも知らせ、「ほら、これが卵やで」と教えてくれた。
Bさんの声につられて、学級の子どもたちがメダカの様子を見に来た。見えにくい姿もあったので、保育者がそのメダカを他の容器に移し、みんなで観察してみた。子どもたちはメダカをじっくりと見ながら、「ほんまや。1個付いてる」「透明や」「小っさ!」と気づいたことを口に出している。しかし、そこからなかなか発展せず、しばらく見ると興味がなくなり、少しずつその場から離れて遊び始める子どもたち。結局、その場に残ったのは発見したAさんとBさん、いつもよく世話をしているCさんの3人となった。
場面2「このままにしてたらあかん!」~自分の知っていることを伝え、共有していく~

- 水槽に網を入れて
卵を取り出そうとする子どもたち 
- メダカの水槽を囲んでみんなで観察
毎日の日課のようにメダカの水槽チェックをしていたBさんとCさん。メダカの水槽に網を入れ、必死にメダカを捕まえようとしている。保育者が「どうしたの?」と聞くと、Bさんが「メダカさん、また卵付けてるねんけどな、ずっと一緒にしていたらメダカさんが卵を食べちゃうんやっておじいちゃんが言ってた。前の卵も食べられちゃったねん」と言う(前に生まれた卵はどこにあるか分からなくなってしまっていた)。 その話を聞いたCさんも一緒になり、「そうなん?! じゃあこのままにしてたらあかん!」「前のやつ、いつの間にか食べられてたんや!」という話になり、慌ててメダカの卵を取り出そうとしていたようだ。保育者も手伝って卵を他の容器に移し変える。BさんとCさんは移し変えた卵を見ながら、「これでいいわ」「あー良かった」と満足気に話している。
次の日、DさんとEさんが「今日も卵付いてるー!」と発見。そこにAさんとCさんが来て、「ほんまや!」「いっぱい!!」と喜ぶ。すぐに「Bちゃーん!!」と呼んで観察を始めた。この卵も移し変え、昨日生まれた卵と一緒に観察している。安心したBさんとCさんは、卵を見つめながら「いつ産まれるんやろ」「何を食べるんやろ」と話している。その会話にDさんとEさんも加わり、メダカのことをよく知っているBさんを中心に、メダカの様子に興味をもつ子どもが少しずつ増えてきた。とても小さな卵を一生懸命に見ながら、「1、2、3、4…」と数えているDさん。この日から卵の成長も観察し始めた。
場面3「メダカさん、ちゃんと目がある!」~発見したことに自信をもつ~

- 「メダカの赤ちゃん、どこ?」

- 「すごいやろ?!」

- 「ちゃんと目がある!! めちゃかわいい」
ある日AさんとCさんが観察していると、小さなメダカの赤ちゃんが産まれていた。ものすごく小さな赤ちゃんのため子どもたちには見えにくく、保育者が「見て、メダカさんの赤ちゃん産まれてるで!」と伝えた。
途端に2人の目が輝き、「えー!!」「どこ?!」と顔をカップにくっ付けて探している。「見えへん!」「分からん!」と大騒ぎしていたが、だんだん集中し始め、2人とも静かになった時、Cさんが「いた!」と話す。Aさんに「ほら、ここ!」と必死に指をさして教え、Aさんが「見えた!」と言うと次は学級の友だちに見せに行き「ほら、赤ちゃん!」と興奮気味に話している。次に職員室へ行って「園長先生見て!」といろいろな人に見せていた。見せながら「すごいやろ?!」と得意気になって、自分たちの発見を話している。
次の日、Cさんは、「ほら先生、見て。めっちゃかわいい。こんなに小さいんやなぁ」と、とつぶやきながらじっと観察している。
- Cさん:「先生!見て。こんなに小さいのに、メダカさん、ちゃんと目がある!!」
- 保育者:「え? どこに?」
- Cさん:「ほら、よく見て!」
- 保育者:「この黒いやつ?」
- Cさん:「うん。ここに書いてるのと一緒やろ?!」と、メダカについて調べて掲示してあったポスターと照らし合わせている。
- 保育者:「よく気づいたね」
- Cさん:「これ(ポスター)見てたら分かったねん」と自分の発見に自信をもって話していた。
- Cさん:その後も、「目が2つある…」と話しながら見つめている。そこへAさんが来た。早速、CさんはAさんに「Aちゃん見て。目が2つあるねんで」と言う。
- Aさん:「えーどれ?」と言いながらじっくりと見て「ほんまや…」とつぶやいた。
考察
- 子どもたちは『メダカが卵を生んだ』という発見ではなく、『メダカのお腹に卵が付いている』という発見の仕方をし、発想の中には『産む』という考えではないようだった。この姿から、見えている現実が子どもたちの考えに繋がっていくことを感じた。いろいろな経験や体験を通して、自然の仕組みに心を動かし、様々な学びに繋げていくことの大切さを感じた。
- 普段はあまり大胆な行動を取ることがないB児だが、メダカとの触れ合いを通して友達から頼られることが増え、様々な姿を見せるようになった。祖父から新たに教わった知識を友達に知らせ、同じ失敗は繰り返さないために自分ができることをやろうと考え行動するたくましい姿に、メダカの飼育が自信へと繋がっていることを感じた。そのB児の姿を見て、周りの友達は、道具の取り合いをするのではなく、固唾を飲んで見守っている姿があり、卵を守ろうとするB児の思いに共感していたのではと考える。
- 必死になって卵を取り出そうとする姿から、卵を発見し、愛着をもっていたB児とC児にとって、『卵を食べられた』ということは衝撃的だったのであろうと予測される。こうした失敗の経験から、「じゃあこうしてみよう」と考える力へと繋がっていく。
- D児は最初の頃はあまり卵に興味を示していなかった。毎日のようにメダカと卵をじっくりと観察することで、愛着がわき、少しの変化にも気がつくようになってきている。対象物に心を寄せることで新たな気づきの機会がたくさん生まれるようだ。
- 自分たちが発見し、助け、守った卵なので喜びも増したのだろう。卵を発見してから、この卵がどうなっていくのかという過程を予測できず、不確かだった子どもたちにとって、『本当に赤ちゃんが産まれた』という驚きもあったのかもしれない。
- 赤ちゃんメダカの小ささを自分の目で確かめられたことで、その『小ささ』により驚く姿があった。そして、それほど小さなメダカの赤ちゃんにもちゃんと目があるということを知り、生命の不思議さや凄さにも目を向けるC児の感受性の豊かさは素晴らしいと感じた。このような感動の出合いや体験を重ねることでますます様々な事物や出来事に関わりたくなるのだろうと考える。
- 初めて見る卵に対しての思い入れや愛着も違い、それは経験の差なのかもしれない。全員が同じ熱量で関わっていくということは難しいが、子どもたちの探究心がくすぐられたり、同じ喜びや面白さを一時でも共感し合えたりする場や機会の大切さを感じた。発見したことを自分だけで留めておくのではなく、友達にも伝えたい、知ってほしいという思いでどんどん発信している。そして、友達から友達へと発見が繋がっていくことが分かった。
- 昨年度の研究(保育者は説明や準備をしすぎないこと)から、あえてあまり手を出さずに子どもたちの主体的な姿を見守ることにした。先を考えず思うままに行動する4歳児の子どもたちだが、一緒に行動してくれる友達や保育者の共感があることで安心して活動し、自主的に行動する姿が見られた。
バックナンバー
- 2022/03/24 匂いへの興味・関心/南丹市立八木中央幼児学園(京都府)
- 2022/02/28 一枚の写真と「科学する心」/こどもなーと保育園(大阪府)
- 2022/01/20 氷~ワクワク感~/幼保連携型認定こども園モロナイ保育園(熊本県)
- 2021/12/20 出合いから広がる探究活動/幼保連携型認定こども園 出雲崎こども園(新潟県)
- 2021/11/24 レーダーチャート化~「科学する心」を見取る~/東広島市立御薗宇幼稚園(広島県)
- 2021/11/01 保育者の振り返りと子どもの気づき/加古川市立加古川幼稚園(兵庫県)