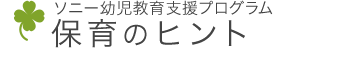![]()
ソニー幼児教育支援プログラム 幼児教育保育実践サイト
保育のヒント ~科学する心を育む~
- トップ >
- 20210729 水の不思議
保育のヒント~「科学する心」を育てる~
水の不思議/姫路市立曽左幼稚園(兵庫県)
 水は子どもたちにとって、とても身近な遊びの一つだと思います。
水は子どもたちにとって、とても身近な遊びの一つだと思います。
今回の事例は、子どもが、ビニールシートの上で発見した雨の水たまりや、水を入れたペットボトルを置いておくことで水の温度が変化する気づきなど、子どもたちの偶然の発見を記録にとり、フィードバックをして、分析・考察しながら「科学する心」を読み取ろうとしている園の取り組みをご紹介いたします。
水のあたたかさを感じて/4・5歳児
- 子どもたちの心の動き
-
出会い:「見て!」「あれ?」「うわぁ!」と感動した姿
躍動:「どうして?」「不思議だねえ」と疑問に思ったり、友達と共有したりする姿
好奇心:「こうなのかな?」「やってみよう」と意欲的に取り組む姿
雨は冷たい(6月中旬/梅雨の時期)

- 手を握って水につける様子
滑り台と登り棒の統合遊具にビニールシートをかけて、雨宿りができるテントを設置した。雨が降った翌日、滑り台に登った5歳児のAさんがビニールシートの上に溜まっていた水たまりに気がつく。(出会い)
「うわぁ!水がたまっとうで」「なんでやろ」「昨日雨降ったからちゃう?」(躍動)とそばにいたBさん、Cさんと話しながら覗き込んでいる。触りたそうにウズウズしていた(好奇心)が、思い切っては手を触れられない様子。
しばらくすると、Aさんが手のひらを少しつけて、「冷たい!」とすぐに引っ込めた。(躍動)
Bさんが、「ええ?冷たいん?」と指を入れてゆっくり触る(好奇心)が、まだ不安なのか、手を握って水につけている。
ふりかえり
保育者は、雨の日にビニールシートの下で遊べたら面白い、と思って環境を構成してみたが、子どもたちは、溜まった雨の方に興味をもったようだった。溜まっている水が雨であることには気づいていたようだが、自然に溜まった水には慎重な子どもたちだった。雨上がりとあって、水が思った以上に冷たく感じ、驚いていた。水道の水が生活の基準になっている子どもたちに、自然と水の関係性で、どのように遊びが広がっていくのかを探ってみることにした。
雨は溜まる(6月中旬)

- 足を入れて水の量を感じる

- ほぼ一緒
雨が続き、雨ふり散歩が日課になっていた。そんな中、園内の水たまりの量が日々違う(出会い)ことに、5歳児の子どもたちが気づく。保育者が「なんで(水の量が)違うんだろね」と尋ねると、Cさんが、「ここだけ雨がいっぱい降っとるから」と言った。そこで、雨を溜めてみることになった。早速ペットボトルを切って、好きな場所3か所に置き、どこの雨が一番溜まるかを試してみた。(出会い)
3時間ほどで、溜まった雨を持ち寄り、同じコップに入れてみた。すると、回収するときにこぼれた誤差はあったが、ほぼ同じ量になった。「あれ?同じやなぁ」「こっちが多いと思たのに」と予想が外れて不思議そうであった。「じゃぁ、なんで水たまりの量が違うんだろうね」と保育者が尋ねると、しばらく考えたDさんが「土が違うんちゃうか?」と言っていた。
ふりかえり
水たまりの水がたくさん溜まっている所に雨が多く降るという発想は、保育者では気がつかないものだった。水の量の違いを先に尋ねてしまった反省と同時に、この経験から、その後も雨の日に友達とどちらがたくさん雨を溜めるか「雨溜め」ゲームにも発展していく様子もあり、保育者の言葉かけを考える場面であった。柔軟に子どもの発想に寄り添う援助を考えていきたい。
ペットボトルの水はあったかい(7月中旬)

- 指を入れて温度を確かめる
水遊びが始まる。遊んだ後に、シャワー変わりになるようにと、一人1本のペットボトルに水を汲み、好きなところにおいてから遊ぶ。(出会い)遊び終わった後に早速その水を体に掛けると、Dさんから、「あったかい!」と声が上がる。(躍動)他の子どもも、「気持ちいい!」と喜んで(躍動)体に掛けていた。
ところが別の曇天の日、同じ場所に置いたペットボトルをDさんが体に掛けると、温度が上がっていなかった。(出会い)
「あれ?冷たいで」「なんで?」(躍動)と言って友達のペットボトルの口に指を付け、「Eちゃんのも冷たいな」と、不思議がっていた。(躍動)
ふりかえり
水遊びの度に、ペットボトルの水の温度が変化することに気がついた子どもたち。場所を変えて、いろいろな温度の変化を楽しんでいた。次第に天気と温度が関係することに気がつき始め、「こんだけ暑かったら(日が照っていたら)お湯になるで」「今日は冷たい方がええから、日陰に置こう」と、好きな温度の水をつくって楽しむようになってきた。梅雨が長く続いたため、予想していた温度にならなかったこともあったが、毎回フタを開ける度に、ペットボトルに指を入れ、自分の水のでき栄えを確かめるのが嬉しそうな様子から、子どもの中にある「科学する心」を感じた。
水は凍る(7月下旬)

- 氷を溶かしてみる
水遊びから氷遊びに発展する。(出会い)子どもたちが好きな花や木の実、おもちゃなども、ビニール袋に入れて家庭の冷凍庫で凍らせて持参して(出会い)くる。入れた時は、透き通ってグニュグニュしていたのに、凍らせると白くなり、入れたものが見えにくくなっていること。グーで叩いても、割れないほど固くなっていることを楽しんでいる。
「冷たい~」「こんなんでてきたで」(躍動)と、氷をたらいの中に入れて溶かしたり、溶けて出てきた花や草を集めたり(好奇心)、と氷の感触を楽しんでいた。
ふりかえり
子どもたちは水が凍ることより、中に入れるものが凍ったらどうなるのかの方が興味深いようだった。
5歳児は花の種類を考えたり、セミの抜け殻を入れたりする子もおり、自分なりに試していたが、4歳児はビニール袋に詰め込むことが面白く、水がほんの少ししか入らなかった子もいた。その氷は、あっという間に溶けてバラバラになり、友達の氷と比べて、なぜ早くなくなったのか、不思議そうにしていた。自分たちで何度も繰り返し試したりして、氷作りを楽しむ様子が見られた。
バックナンバー
- 2022/03/24 匂いへの興味・関心/南丹市立八木中央幼児学園(京都府)
- 2022/02/28 一枚の写真と「科学する心」/こどもなーと保育園(大阪府)
- 2022/01/20 氷~ワクワク感~/幼保連携型認定こども園モロナイ保育園(熊本県)
- 2021/12/20 出合いから広がる探究活動/幼保連携型認定こども園 出雲崎こども園(新潟県)
- 2021/11/24 レーダーチャート化~「科学する心」を見取る~/東広島市立御薗宇幼稚園(広島県)
- 2021/11/01 保育者の振り返りと子どもの気づき/加古川市立加古川幼稚園(兵庫県)