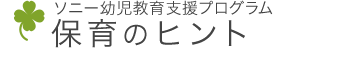![]()
ソニー幼児教育支援プログラム 幼児教育保育実践サイト
保育のヒント ~科学する心を育む~
- トップ >
- 20210415 命の誕生~カタツムリ~
保育のヒント~「科学する心」を育てる~
命の誕生~カタツムリ~/社会福祉法人五倫会美郷こども園(青森県)
 散歩先や園庭で見つけた身近な生き物と、皆さんの園の子どもたちは、どのような関わりをしていますか?
散歩先や園庭で見つけた身近な生き物と、皆さんの園の子どもたちは、どのような関わりをしていますか?
保育室で子どもたちと身近な生き物を飼育し、観察したりお世話を通して愛着を感じたり、クラスの大切な存在になっているエピソードは多いことと思います。
今回は、身近なカタツムリをクラスで飼育しているうち、新たな命が誕生する場面と出合い、3歳児なり関わり、クラスでカタツムリへの思いを共有していく事例をご紹介いたします。
「交尾から赤ちゃんの誕生まで」/3歳児
かたつむりの交尾(6月28日)
 「先生、カタツムリチュウチュウしてる」見に行ってみると、2匹のカタツムリが今までに見たこともないような形(体勢)をしている。カタツムリの本を出してきてみんなで見て、交尾だと知る。調べてみると、カタツムリの交尾は何時間にも及ぶということだった。そして、交尾から約1か月で産卵となった。
「先生、カタツムリチュウチュウしてる」見に行ってみると、2匹のカタツムリが今までに見たこともないような形(体勢)をしている。カタツムリの本を出してきてみんなで見て、交尾だと知る。調べてみると、カタツムリの交尾は何時間にも及ぶということだった。そして、交尾から約1か月で産卵となった。
産卵に向けて
「子どもたちと一緒に新しい命の誕生に出合うことができるかもしれない」と保育者は子どもたちとカレンダーを眺めながら出産予定日に赤い丸をした。卵が産まれるのを指折り数え、産卵しやすいように環境を整えていった。
産卵(8月11日:交尾から44日目)
「子どもたちが「先生、カタツムリが卵、産んでる!」と言いにきた。見るとカタツムリが土の中に卵を産んでいた。絵本や図鑑で見たままの産卵シーンだった。まっ白いたくさんの卵を見つけた子どもたちは、みんなで大喜びする。ここから約1か月で赤ちゃんカタツムリに会うことができるが、カタツムリを孵化させたことがない子どもたちと保育者は、「無事に赤ちゃんが誕生できれば」と祈るような思いだった。
孵化(9月18日:産卵から38日目)


「いつものようにカタツムリに「おはよう」と声をかけた。すると「先生、赤ちゃんになった」といつものトーンで教えてくれる子どもたちの声がした。
その数秒後、「先生! カタツムリの赤ちゃん産まれた!」と悲鳴のような声に替わり、カタツムリの周りは子どもたちでいっぱいになった。
「ちっちゃい」「かわいい」「超かわいい」「ちゃんとクルクルある」「目、出てきた」「伸びた」と思い思いの声があがった。
「ハッピーバースデートゥーユー ハッピーバースデートゥーユー ハッピーバースデーディア赤ちゃん ハッピーバースデートゥーユー」と、みんながカタツムリに向かって歌っている。
カタツムリの赤ちゃんが産まれたことで、子どもたちに一体感が生まれていた。
それぞれの思いとかかわり
赤ちゃんが産まれた次の日、園舎の隣にある畑に行く。今年は、ナス、トマト、オクラ、ピーマン、パプリカ、サツマイモなどの苗を植え、水をかけたり、草を取ったり、収穫したりとみんなでお世話をしてきた。畑に行った子どもたちは、それぞれにナスやトマトを収穫し、手に持って帰ってきた。
 園舎に戻り「園長先生ただいま」と言うと、そのまま子どもたちは保育室にまっしぐら。保育者は子どもたちの後を追って、保育室まで行った。カタツムリのケースには、収穫してきたばかりの野菜が全て入れられている。子どもたちは、「今採ってきたから食べてね」「超おいしいよ」と口々に声をかけている。保育者に、いろいろな気持ちが巡る。純粋にカタツムリと向き合う姿、取ってきたものを「おいしいよ」と飼育ケースに全て入れる姿など、3歳児の子どもたちにとっては友達のような存在なのだろう。赤ちゃんが産まれた時に、ハッピーバースデーの歌を歌っていたことが思い出された。
園舎に戻り「園長先生ただいま」と言うと、そのまま子どもたちは保育室にまっしぐら。保育者は子どもたちの後を追って、保育室まで行った。カタツムリのケースには、収穫してきたばかりの野菜が全て入れられている。子どもたちは、「今採ってきたから食べてね」「超おいしいよ」と口々に声をかけている。保育者に、いろいろな気持ちが巡る。純粋にカタツムリと向き合う姿、取ってきたものを「おいしいよ」と飼育ケースに全て入れる姿など、3歳児の子どもたちにとっては友達のような存在なのだろう。赤ちゃんが産まれた時に、ハッピーバースデーの歌を歌っていたことが思い出された。
ふりかえり
子どもたちがカタツムリに毎日声をかけ、友だちとして触れ合う中で、「あれ?」と変化に気づいたり、「よし」と行動に移してみたりと、自分なりに愛着を深めていた。また、カタツムリを思いやり、何をすると喜ぶのかを3歳児なりに考えている姿が見られた。
子ども達との生活を続けていく中で、もう少し踏み込んでみたいという思いがあったものの、3歳児の子ども達とはもう一歩踏み込むことができなかったもどかしさもあった。そこですべき保育者の役割や、声掛けがあったのではないかと反省点もある。保育者優先になってはいけないが、働きかけがなければ気づけないこともある。十分な知識と、実践できる環境、子ども達の目線での探究心を持ち合わせ、いろいろな活動に向き合っていく必要がある。この思いを次への取り組みへとつなげ、園全体で子ども達に科学する心を育んでいきたい。
バックナンバー
- 2022/03/24 匂いへの興味・関心/南丹市立八木中央幼児学園(京都府)
- 2022/02/28 一枚の写真と「科学する心」/こどもなーと保育園(大阪府)
- 2022/01/20 氷~ワクワク感~/幼保連携型認定こども園モロナイ保育園(熊本県)
- 2021/12/20 出合いから広がる探究活動/幼保連携型認定こども園 出雲崎こども園(新潟県)
- 2021/11/24 レーダーチャート化~「科学する心」を見取る~/東広島市立御薗宇幼稚園(広島県)
- 2021/11/01 保育者の振り返りと子どもの気づき/加古川市立加古川幼稚園(兵庫県)